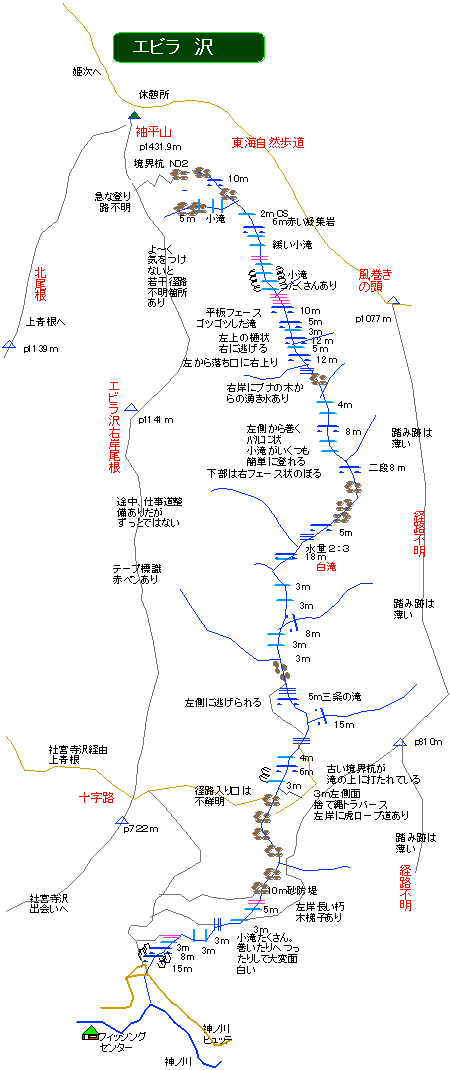丹沢の沢歩き 神ノ川 エビラ沢 Ⅴ は遠いと泣くマシラ
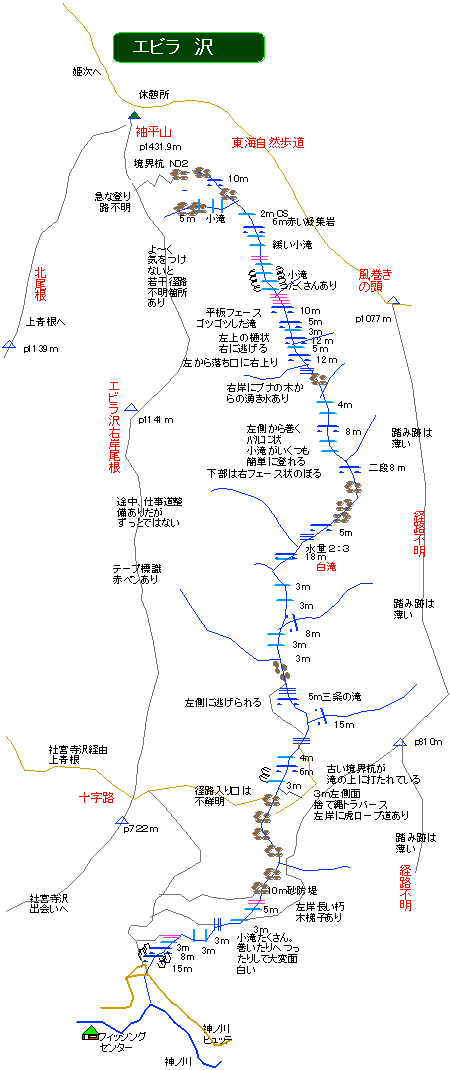
素が凶暴、
それもあっただろう。しつけの怠慢が主因とも
とはいえ、13発の弾を受けてと聞くと哀れみを感じないか。
野生が制御できなくなった犬
それでも
撃った者の本心は知り得ないが、命の哀れを知っているなら、相手を誅する場合には一発必殺で始末しなくてはだめだろう。
稚拙からそうならざるを得なかったとしても一匹に向かって至近からの13発なんてのは、サディエストがもだえ苦しむのを楽しんでいたのと同じではないかといらぬ憶測を俺に想像させる。
残虐な刑罰は避けなくてはならない。
人に対してだけでなく、生きる物に対しても同じように努めなくては。
法に定められ、限られた者しか手にすることが許されていない道具を使う者はしっかりと使い方をマスターして無用な苦しみ与える前にきちんと始末してくれよ。
それとも俺にピストルを預けてくれるかい。
もしも2年前に持たせてくれていたら、三発であいつらを始末して、犬には苦しみ与えず、まして自分自身が咬まれるなんてだらしないざまを呈することなく、硝煙の匂いが少し漂ようその場を 悠然と去り、何事もなかったかのように悠々と沢歩きをしていただろう。
グレーグ東郷ここに見参 そんなこと ないよ
そんな 昭和気分は遠い昔のこと
小林旭か、赤木圭一朗にでもなったような言い方
やめとけよ マシラさん
 秋色の宮ヶ瀬湖
秋色の宮ヶ瀬湖
犬好きであり、生き物には憎まれない性格と自負していたのに、
そんなのあんたの思いこみ以外の何ものでもないのを白日の下に晒した事件が
かって神の川林道であった。当事者はマシラ本人だ。
あの時、行こうとしてたのはエビラ沢だった。
後味まずい記憶を何かで上書きして消さなくては。
本日、エビラ沢に行く理由は以上だな。
なのに
集落はずれの家の前を通りかかった時、犬が吠えた。
鳴き声の方向をチラッと見ると犬小屋があって、その外で黒犬が吠えていた。
見覚えがある犬だった。つないであるので飛び出しでは来ないが、あのときは三匹だったが、一匹だけらしい。
もしもその一匹単独で来るならと、殴り殺してやるぞ
あたりに丸太が転がっていないかと目がさがす。
なんか、俺って殺気立って
さっさと走り去ればよいことなのに。
いやなことを思い出した。
あの日の治療は第三者による怪我のため保険は適用されませんとのことで全額自己負担だった。
連絡したが、飼い主からは■千円限定で勘弁してくれとのメールがあったのみ。
その後は無し、
あきれて、それ以来放置してしまっている。
もしも今日の犬が放し飼いなら、期限ぎりぎりだが、あのときの件を少額訴訟でうんぬんとの考えもあってもいいかもなあと。
まあ、
つないであったのだから、よしとして済ませて前のことは忘れよう。
なんて言いながら、コソッとここに経緯をちょこっと書くなんて結構粘着質だよね マシラ
たしかに気持ちをそう切り替えようとしても、忘れるどころか、あのときの忌々しさが思い出されて、こんなんじゃあ今日も先行きが思いやられる。
でも
忘れると決めたのだから、さっさと忘れろよ!
気分を変えるためにもペダルを強く踏んで、さっさと次行こう。上空は青いが、大室山の山頂には帽子雲が乗っている。
 エビラ沢F1
エビラ沢F1
神之川キャンプ場(社宮司沢出会い)を過ぎて次のカーブを曲がるとエビラ沢橋だ。
東屋に自転車を止めて、F1を眺め、支度を整えたら左側の小坂から出発する。
小坂には六寸角の木梯子があったはずだが、滝壺に残骸が落ちていた。
エビラ沢は何年かに一回は来ている。
だけど未だF1・F2登ったことがない。
だから沢登りではなく、沢歩き。
F2の上に一度降りたことはあるが、それだけで白滝も登ったことない。
若い頃なら巻くなんて事しなかっただろうが、そのころは北丹沢に入る時間があるならば、一ノ倉に行っていたはずで、山も色々選べるほどに暇ではなかった。
だからその当時は、こっちに来たことがなく、一人で沢歩きを楽しむようになってから来るようになったのだが、もう登攀の範疇の滝は登れなくなっていた。
これらの滝を登らないとなれば、困難度C級であっても沢登り的にはレベルが落ちるのは当然だ。
でも沢歩き限定であっても、綺麗な滝は眺められるし、小滝は数えるのが面倒なくらいに沢山あるし、水が多く歩くだけでも楽しめて、マシラのぶらぶら沢歩き(沢登りではなく、難しい滝には登らない手抜き歩きというジャンル)には似合いの沢だ。
小石が乗って滑りやすい滝横の小坂を登り、左手から流水崩石溝を横断したら、右斜面にくくりつけられている木梯子を登る。
21世紀に入った頃に新設されたこの梯子、下部の跨木が何本か割れて抜けたが、しっかりとした作りであったので、いまだしっかりしていて頼りになる。
ただし表面は中から浮いて油分でヌメヌメとしているので、滑らないよう用心して登る。
梯子を二つ登ると出っ張る露岩の間を整えた坂の道に続く。
この二回目の曲がり角から1m沢側に移動する。
地面は安定しているように思えるが、そこは露岩の間に溜まった土と枯葉で出来た空中に出来ていて、それに気がつくと地面が抜けはしないかと何か掴まっていないと不安に思うような場所。
そんなだが、正面横にはF2が見える。
F2はスベスベの岩面を、大量の水が左右にわずかな弧を描くようにして、水は岩とは離れずに滝壺に落ちて激しく波打つ。
その勢いのままに、水は下(F1)に飛び出しているのが見えるような気がするが、何せ急な場所の厳しい眺めなので余裕無く、見えているままを正確によりも、50%くらいは水煙で半透明なのを想像で補って、さもありなんと書いている。
もう少しは正確に落ち口の様子を見ようと、一段上のF2落口に降りる露岩に立ったが、風景に変わりがない。
また、そこからの3mのF2落ち口への下りは厳しいと知っているので降るのは止めておく。
滝見はそれくらいにして、岩尾根が終わるまで経路を上がり、水平部から下に降りる易しい道で沢に降りて、そこから沢歩きが始まる。
エビラ沢はF2の上から白滝までの間は沢山の小滝とナメ、それをゴーロでつないでいる。
沢に戻って見えるのは、左右を岩壁に挟まれた小さなゴルジュ状である。
右岸の丸みを持った段々の緩い傾斜面の大スラブを歩いて抜けて行くことになる。
乾いていれば快適だ。
そのスラブの窪みには泥が乗っていて、それが、一昨日の雨を吸ったせいか、乗ると水分をはき出し、泥田の様にグジュグジュとつぶれて泥が溜まるくらいに僅かな傾斜なのに靴が滑って踏ん張りが利かない。
 F1F2を巻いて堤防上で沢に戻ると
大きな滝はないが、小滝と深い釜の連続帯となる
F1F2を巻いて堤防上で沢に戻ると
大きな滝はないが、小滝と深い釜の連続帯となる
「おっとっと 滑る」
岩にしがみつきたくとも丸みを持った岩には確かに掴めるところが何処にでもあるのではない。
横に行き詰まったからと上がると下までの距離が高くなってしまって危険だ。
フリクションさえ利かせることが出来れば易しいが、このように本日は出だしから緊張の沢歩きだった。
もっともゴルジュに飛び込んで泳ぐ気さえあれば、
小滝を超えるだけであって、易しいところだが、日が差し込まないで冷え冷えとした感じの漂う谷間、一人そこに立つと、そんな気になれない。
それでも、そこで緊張したので、濡れずに行くよりも水に入る方が易しいなら、この先はそうすべきと思い直す。
だから岩床に戻った一歩目からが水の中だった。
水は冷たくない。気分も悪くない。
入れば入ったで、水の冷たさは何ともないのはいつものことで、どうせそうなるなら早めにすべきとは分かっていても、沢で靴を濡らすのがへたくその証し。
そう水無川の沢登りで教えられた昔の山屋であるマシラにとっては、最初の一歩目から躊躇うことなく飛び込むのは、どうしても出来ないことであって、少し困ってその成り行きに従ってやむなく水の中に入るのが常であり、今日だってそうだった。
夏でも無し。
本日は泳ぐのだけは無しだ。
エビラ沢は飛び石するよりも水の中の方が安全で歩き易い。
だから腰の下くらいまでなら水に入って、10カ所ほどの小滝を登り、小釜は浅いところを探って突っ切って、それでしばらく歩くと岩床の上に築かれた砂防堤に着く。
 小滝 釜 水
小滝 釜 水
 小滝 釜 水
小滝 釜 水
 下流帯の砂防堤は岩床の上に堂々と立つ
砂防堤上からはゴーロだ。
下流帯の砂防堤は岩床の上に堂々と立つ
砂防堤上からはゴーロだ。
砂防堤の上はゴーロから始まる。
右岸から経路が入ってくるはずだと探りながら歩いたが分からなかった。
ゴロ・ゴロ石のゴーロ石が中くらいから大石が岩床の上に乗るようになって、それが小滝に変わり、その先で深い釜の3mcs滝に至る。
左岸にトラロープが下がっているが、ここは右岸の水平溝を使う。
前回(2012年)は釜が深くて、その溝に入るための捨て縄(テープ)に手が届かなくて苦労した。
今日は幾分か浅かったが、ちょっとだけ足りなかったので、その分を石を二つ積んで補う。
一つ目に届くと、それを頼りにして次のにも簡単に手が届く。
溝の天井は低いが、頭を少しは上げることも出来るし、見渡すと足場もそれなり、最初の捨て縄さえ切れなければここは難しくはない。
この残置のテープ、天井付きで雨に濡れることは少なく、まだ使えるとは思うが、十数年以上も前に誰かが残したままのものだから、一連の四カ所、もうそろそろ更新した方が良いとは思う。
でも前回もそうだったが、通り抜けちゃってから、そう思いはしても行動には結びつかないマシラである。
 沢幅が狭くなってゴーロが小滝に変わる
沢幅が狭くなってゴーロが小滝に変わる
 3mの小滝
左の側壁 水面上3mを奥行き60cmで削り取ったような溝を
匍匐して前進する。
(左岸にも虎ロープ道あるので無理は無しでも可)
3mの小滝
左の側壁 水面上3mを奥行き60cmで削り取ったような溝を
匍匐して前進する。
(左岸にも虎ロープ道あるので無理は無しでも可)
前方に6mほどのナメ滝が見えてくる。
ここは右側から回り込む。
その右側を上がったところに木製(昭和39年)とコンクリ製(No82)の道界柱二本がともに倒れていた。
この標識、ナメ滝の下から「あそこに何かある」と目立った標識だったが、上から流れてきた土砂に押されて倒れたらしい。
プレートはどちらも文字鮮やかだが、近いうちに砂に埋もれるか、沢に押し出されて無くなってしまうだろう。
 倒れてしまった神奈川県企業庁の木標
金属プレートの文字は錆びもせず
倒れてしまった神奈川県企業庁の木標
金属プレートの文字は錆びもせず
そこからいくらか進み、ゴトゴトした岩床の上で沢は左に小さく曲がる。
曲がりが直った所に三条に分かれて水が5mほど落ちる。
右二条は急なのでマシラには登れそうもない。
左の一条に水が流れてない時に登ったことがあるが、今日はたくさんの水を落としていて、ダメかなと近寄ってみたら、流路の右がホールド豊富だったので半身に水を浴びながらも快適に登る。
 ゴツゴツした岩床
右から湧き水が吹き出し
空からは日が谷間に差し込む
ゴツゴツした岩床
右から湧き水が吹き出し
空からは日が谷間に差し込む
 三条に水が湧かれて落ちる
左の落水の右が快適だった、
三条に水が湧かれて落ちる
左の落水の右が快適だった、
小滝、ゴーロと続き、次に左岸から水が落ちてきて、更に小滝、飛び石、小滝の登り、難しいところは出てこなくても、沢が狭まってきてもうそろそろかな、と思う頃に白滝が見える。
右岸の岩尾根が閉じかけの前門のように沢幅を狭めて滝の下を隠し、その岩は前門の2m小滝につながって滝の露払いを行っている。
落ち口の上には青い空が見えている。
 ゴーロ帯
木々により日が遮られてた暗い沢の中
木漏れ日が水流に燦めく
ゴーロ帯
木々により日が遮られてた暗い沢の中
木漏れ日が水流に燦めく
 再び 岩が出てきて小滝があって
もうそろそろと
再び 岩が出てきて小滝があって
もうそろそろと
白滝は名瀑である。
岩は黒いが白滝である。
堂々と落ちる水が泡立って白く見えるから白滝なのだろうか。
実際に登ったことがないので、ロープの繰出長では高さを示せないが、落差は20mを越えるほどだろう。
滝の本体はツルツル垂直一枚岩のスラブ、左右に別構成の岩を伴っていて、全体ではそれなりに幅があるが、前門で3m程に狭めされているので、落水で生まれた風が滝と前門の岩との間の狭い空間に集まり、空気の圧力が高まってから隙間から吹き出す。
だからか前門滝の正面に立つと身が凍えるほどに風が強く当たる。
中に入るとそれに滝からの飛沫が混じる。寒い。
だから正面に立つのは止めて側面壁寄りに近づいて、そこから首を大きく上に扇いで落ち口を見上げる。
そこは風がたまり場となっているので渦は感じても風の流れはいくらか弱まってる。
滝は登るなら右側の岩場である。
前に来たときには、白く色の抜けた残置紐の何本もが見えていて、あの残置をリレーすれば無手勝流でも登れるのではと無いかと思ったほどだが、今日は暗くて細部がよく分からず、変わりに、絶望的に急な岩壁にかぶる落ち口にオーバーハングして、上には青い空が見えていているばかり。
登れるような雰囲気は微塵も感じない。
同じ滝でもその時その時出ず言う分と印象が変わるのだ。
滝は変わっていないのに、変わっているように思うのは見ている者の目ってことだね。
存分にマイナスイオンを感じたら、次へと行かなくては。
前門の小滝を下るのが面倒なので、滝壺部から直に左岸の岩尾根に出る。
すぐそこに白滝を眺めつつ登れる。
この岩尾根上の巻き道は眺めは良いし、木の根っ子などの支点もしっかりしていて、悪くない。
 白滝
白滝
 白滝 登攀ルートを滝壺から真上に見上げるが
日が遮られて、細かい凹凸は分からない
白滝 登攀ルートを滝壺から真上に見上げるが
日が遮られて、細かい凹凸は分からない
二俣
白滝を終えると沢が二分する。
左も水流が多いが、右が本流だ。
ゴロ中に倒木が多い。
煩わしくても前に進む。
倒木と倒木の空間の広そうな所に体を押し入れ、手で枝を広げて抜ける。
簡単な滝を二つ・三つ行ったか。
小滝はシャワーに至るまではないが、飛沫程度は受けて登る。
 シャワーが強くて本来コース(水流左側)はちょっと避けて
右側から回り込んでから滝の中央に出て登る
シャワーが強くて本来コース(水流左側)はちょっと避けて
右側から回り込んでから滝の中央に出て登る
次は8m程滝だ。
ゴツゴツ感のある岩で出来ていて、傾斜は強くはない。
直登を考えたが、水量が多く、中央あたりで岩に跳ねられた流水を全身に受けるように思えて右側のザレを5mくらい登ったところから(一カ所スラブあり 足が決めずらく手こずるが)滝の中央に出て残り部分は滝を登る。
そこからは小さな凹凸で覆われた岩床がしばらく続き、そこの中央を気持ちよく歩いて行く。
谷間の中央になんとなくだが、稜線が感じられるようになる。
そして岩床の上には滝が立ちはだかって、奥の滝場が始まる。
 奥の滝場所の最初の滝
左側から右上がりの草溝バンドから落ち口に出る。快適
奥の滝場所の最初の滝
左側から右上がりの草溝バンドから落ち口に出る。快適
 二番目の滝は右側から小さく巻く
巻き道は岩の間の小さなテラスを木の根っ子で強引こ繋いで登ることになる
落ち口に降りる3mがちょっと悪いのでロープを使った方がよいかな
二番目の滝は右側から小さく巻く
巻き道は岩の間の小さなテラスを木の根っ子で強引こ繋いで登ることになる
落ち口に降りる3mがちょっと悪いのでロープを使った方がよいかな
最初のは10m程である。
滝の本体も登れるはずだが、脆そうな岩であり、無理は禁物として、左側から右上がりに落ち口にでる草付きバンドを登る。
このバンド、難しくはないが、剥がれているのもあるから慎重に行く。
ナメ状を挟んだ次の滝も10m程はある。
下の滝よりは急なので、考える事無く巻く事にする。
巻き道は右側の側面を少しだけ登り、そこから崩れ気味斜面を滝側に横断して、落口方向に進むバンドに出て木登りの要領も含んで岩場を繋ぐ。
真下が滝であって、高度感があるが、滝の高さを超えるまでは根っ子も立ち木も岩もしっかり確かだ。
だたし、落口を僅かに過ぎた所から3m下るところの一カ所だけが掴むところが無くて、ここで滑ったら巻いた滝の下まで落ちる可能性もあるかと、そうためらいつつ下ったが、降りて見直すと、上からは見えないところに、しっかりと足をおけるスタンスがあって、始めからそれと分かっていれば難しく感じることはなかっただろう。
 5~7mの滝
急だが、水平な節理が豊富で、普通に登ればよくて快適だ
5~7mの滝
急だが、水平な節理が豊富で、普通に登ればよくて快適だ
 左上がりの滝
何処でも可能だが
中央の岩が登るには良いだろう
左上がりの滝
何処でも可能だが
中央の岩が登るには良いだろう
その次の滝は5mほどの急傾斜滝だ。
でも水平で指のかかる節理岩だし、高さも5m程だから、急であっても快適の一言ですむ。
次の左上がりの樋状滝は、今までこの沢を歩いていて、この滝には僅かに水が垂れるくらいであって流水というほどの事はよほどでないと無い涸棚と思っていたが、そうでもなさそうだ。
正面の岩場が等間隔にスタンスがあるので、これも快適な岩場登り。
エビラ沢の上流部には、源流帯と言っても良いほどの奥に、石積みの砂防堤がある。
全部で三つ。
一番目のが一番大きい。
大きめの石を5~7段につんだ5m程の高さの堤である。
角をそろえて、いささかもほつれが見えない堤は素人作りではなく、職人の手によって築かれたものであり、ものすごく古い物ではないと思う。
俺に想像できるのは、山奥での作業が大変だったろうって事くらいだ。
里から離れて、上り下りに時間がかかるところだから、近くの水の取れる山の平坦部に簡易宿泊所を作って寝泊まりして作ったことが想像できる。
でも誰が何を目的に作ったのだろうかとなると、もう分からない。
下流の集落への洪水防止には余りにも離れすぎていて、ここでの構築は実効性ないだろう。
だとしたら白滝より上流帯の洪水防止が目的だったのかなあ。
堤を作る労力を上回る価値があそこ等にあっただろうか。
先ほど歩いてきたところを思い出しても、そこにはゴーロがあっても、切り出したら高く売れるような美林があったようには見えなかったけれどもね。
ここらは民有地ではなく、企業庁の管理地らしい。
マシラの今の価値観で考えるとそうなるが、昭和30年代、ここらでも大伐採がされた事がありと聞いたことがあるような気がする。
林業が戦後日本の復興を支えていた時代なら違った価値感があったろうし、
この堤より下流の広いゴーロも、今のような雑木がまばらではなく、
財産価値ある銘木の美林であったのかもなあ。
考える持ちネタの少ないマシラが考えるのはそれくらいだ。
 上流帯の小さな石積み
しっかり組んで積んた堤はいささかも綻びなし
上流帯の小さな石積み
しっかり組んで積んた堤はいささかも綻びなし
一番目の砂防堤と、次の砂防堤の間の、どれも登るのが課題になるようなのはない。
でも数えるのが煩わしいほどのたくさんな小滝を登り、三番目の砂防堤が終わると、稜線がもうそこに見える。
エビラ沢の沢歩きは、おおよそ4時間だ。
丹沢の沢の中では長い方だ。
この先には大棚は、無いということも分かっている。
水気のある左手の支流に入り、右に涸棚を見て、その直ぐ先のボサが多くなりそうな感じのするところで沢に分かれて、左手の小尾根に移る。
こんな所の小尾根でも、人が踏んで開いた感じの踏み跡道があり、沢登りの詰めとして、多くの人が辿っているのを想像する。
灌木があっても下草は少ない、馬酔木の枝に引っかかる事は何回もあるが、突破するのが面倒なというようなことはない。
右から上がってきた隣の尾根の上が剥げている。
そこまで距離は50mか。
そこの赤土に刺さる赤黒の境界杭が見える。
あそこは登山道(経路道)だろう。
 小滝を越えて源流帯に入る
山は、少し色が付いて
もう暫くすれば綺麗な紅葉になりそうな気配
小滝を越えて源流帯に入る
山は、少し色が付いて
もう暫くすれば綺麗な紅葉になりそうな気配
でも最後までここを詰めて、ダイレクトに袖平山に出るのも悪くない。
そう意気込んで登るが、小尾根は無くなり、斜面を登っていくとNo4の境界杭のところで登山道に行き当たった。
赤土上の伏石部を通過して、登山道を短くたどって、緩い斜面が緩んだところのNo1杭の向こうに山頂標柱がたっている。
唐松の季語は知らない。
でも落葉するから唐松は秋の木だと思っている。
9月は秋には少し早いのかも知れないが、里では栗が農家の庭先に並べてあるし、畦には彼岸花咲いて棚田では稲刈りも始まっていて、そんな中で具体的に秋を探るなら、青い空を背景に唐松の木が映える袖平山は、ここらの山で一番濃く秋を感じられる所であって、この季節にはもっとも相応しい山頂だと自分でははずせない山だ。
その期待通りに、上空の青空に雲が風に筋を描いて流れ、それの手前にすくっと立つ唐松は期待通り。
枝越しに細い雲が見えていて、先端に定期航路の飛行機がぽっかり浮かぶ。
 袖平山 山頂
袖平山 山頂
風巻ノ頭もそんな感じかな。
神の川が日だまりの中を流れる。
目を水平にして見る檜洞山、大室山は山頂付近までは姿が見えても、富士山はちいさな積乱雲の固まりが前面を覆っていて見えない。
そうであれば姫次まで行って眺め直す気力も湧かない。
山頂を示す標柱横に落ちていた[←エビラ沢橋/社宮司]の標識を手に取ると、
地面との間に巣くっていた蟻が、板の移動をお前の自由にさせては俺等には大迷惑とばかりにたくさん舞い寄ってきて顔の回りが騒がしく、這々の体でその場を離れる。
山頂から10m離れたところの東野方向の標識はぜんぜんOK。
山頂から10m離れてセットされているエビラ沢橋方面を示す標識は以前に括り付けた覚えのある捨て縄の色は抜けたが、これもまだ大丈夫だ。
エビラ沢橋に向かって下る。
赤土の石伏せ部からの暫くの間、下り道は堅い土が水を吸って泥のようになっていて滑りやすい。
綿ロープはだいぶ黴びているが、触るだけなら大丈夫だ。
ありがたく使わせてもらって急な部分をやり過ごすと、傾斜はなだらかになって、それからはずっとよい道だ。
あんまり調子に乗って、とばすと不意の遭遇もあるかと、役に立っている実感は全然感じないが、赤黒境界杭のタイミングに合わせてホイッスルを吹いて一応は用心しておく。
中間くらいからは作業道が斜面に切ってあった。
路肩丸太の下の砂が抜けている所も多く、まじめに歩くとそこに落とし穴に嵌るようになりこともあって、ええい面倒だと中間をショートカットしたくなるが、見通しの利かない山腹をこの手抜き行動によって何度も道を失って困っている。
ここらではまだ山は深く、とんでもないところを下るのを強いられることもあるからと我慢して忠実に下る。
中間部下からは緩い傾斜面に踏まれた経路、路肩は無く、枯葉が乗っているが、多くの人に歩かれて堅く踏み固められて道であり、不安定な石ころはなく、根っ子など飛び出していない道。
この踏み道、杉の植林帯中の尾根をこのまま沢に入ってしまうのでは無いかと言うくらいな大きな折り返しで続いていて、いかにも里の山道を歩いているとの気分が味わえる気分がよい道だ。
こういう道は何時までもこのままの状態でもって欲しい。
ショートカットは無用だ。
径路中の十字路
正面は社宮司沢出会いへ
右折は上青根への経路(黒線道)
左折はエビラ沢への十字路鞍部に至る。
(戻れば袖平山)
ここから上青根に行ったこともあるが、あのとき、社宮司沢に降りるまでがちょっと分かりにくかったような
それ以外の部分は固められて間違いのない道だった
 エビラ沢橋に向かって降る
しっかり踏んである歩きやすい道が
心楽しくさせてくれる
エビラ沢橋に向かって降る
しっかり踏んである歩きやすい道が
心楽しくさせてくれる
今でも行けるのかな。
30mだけ入ってみたが、戻って、エビラ沢橋への道に入る。
自転車をそこに置いてあるのだから、コースに選択の余地はない。
このように自転車や車で来るのは便利なようで、でも、行きたいところがあっても選べないという悪さがある。
まあ下ってからの一・二時間の労力を惜しまなければ、そんなの制約ではないのだが、せっかちなマシラにとっては、わざわざ遠回りして車道を戻るが、余計で無駄に時間だと思わせる。
そうした労を惜しんで、稼せいだその時間を何か人生に有益なことしているかと言えば、家には早く帰ることにはなっても、何もせず価値も生まずだから、そのほうが余計に無駄時間なのかも。
十字路からエビラ沢橋への道は悪くない。
ただし、エビラ沢と社宮司沢出会いに下る尾根の中間の傾斜面に道は設けられていて、下から沢音が聞こえてきてからは結構急な地形に付けられていて、所々で土石に道が流れてしまっている。
砂利に足をすくわれたら下のエビラ沢まで一直線にすべり落ちることもあるように思える。
朝から歩いていて疲れているだろうから、かなりな注意力散漫な時間帯だ。
そんなときは目では見えていても、意識がゆるんで浮き石を無視して踏み上がって転ぶなんてのも多い。
だから慎重に行けと言い聞かせるが、それで本当に慎重になっているかどうか、しっかり見張っていいるかの自信はない。
下からの沢音が滝の轟音に変わり、下方にエビラ橋横の東屋が見えてきて、岩尾根上の経路からF2落口を目の下に確認する。
F1下までは直ぐだ。
滝壺で泥を落として見繕いを行い、東屋横の水場で喉を潤す。
車が何台かと降りすぎたが、みんな停まりもせずに、さっと通りすげてい行ってしまう。
昼飯時だ。
皆さんそれぞれ約束の集合時間に急いでいるんだろう。
走り出して直ぐの神之川キャンプ場はBBQテーブルが川縁一杯に広がっていて、焼肉の煙がそこら中に漂っていて、たくさんの人が昼飯の最中だった。
腹減ったね。
俺も減ったよ。
帰って飯を食べよう。
だけど情けない。
帰りはなすがままの走りだ。
たかが、ひとつ山を登っただけなのに、帰り道のペダルを強く漕ぐ力が湧いてこない。
ほとんどが下り坂、それに追い風だったのに、所々にある登りでは、いつもよりも二段ほどギアを軽くして、力を入れずに停まらないで走れる最低速で行く。
そんなでも、幸いに今日は連休初日であって、山中方面に向かうチャリには沢山行き交うが、俺と同方向に走るのは皆無であり、他人を意識することなく、マイペースでずっと走っていられるのがよい。
それでも梶野から鳥屋谷戸に抜ける坂が何時もより急で辛い。
鳥屋から鳥屋園地までの短い坂が辛い。
坂道を下るときは、たいした坂ではないと思うのに、登りではちょっとしたのも急坂に感じる。
社会の支え合い、ご近所の助け合いなどの自分への追い風は当たり前だと思い、向かい風、世間の冷たさには過敏に感じるタチが坂道にも同じように反応してしまっているらしい。
鳥屋園地で一息ついて帰ることにした。
予定より一時間短く早く家に着いたから山も自転車も悪いペースではなかった。
以上、シルバー・ウィーク・初日
自宅5:35~宮ヶ瀬6:30~船津原~エビラ沢橋(自転車デポ)7:35~エビラ沢(F2上から沢に入る)~白滝9:10~沢を出て小尾根に乗る11:10~右岸尾根に入る(道界No4)11:20~袖平山11:25~下の休憩場~袖平山11:40(エビラ沢橋への登山道に入る)~上青根分岐12:10~エビラ沢橋12:30~宮ヶ瀬(鳥屋園地休憩)13:35~自宅14:25 2015/09/19
頁トップへ マシラのhp