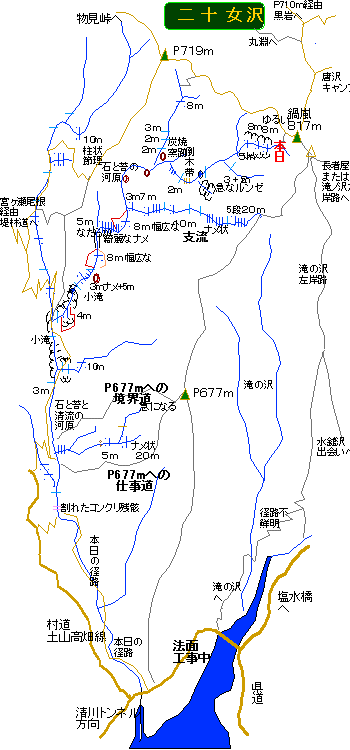丹沢の沢歩き 宮ヶ瀬中津川支流 二十女沢(ハタチガさわⅦを歩くマシラ
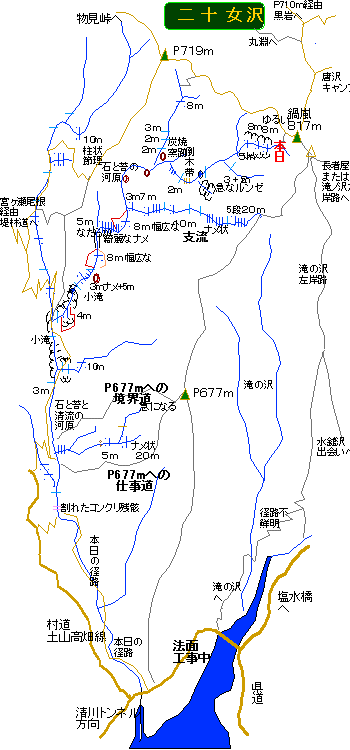
今年、すでに
7月に下降ポイントを間違って、ハタチガ沢は歩いてた。
滝ノ沢を登った下りにクジラの背尾根の中途にある小ピーク677mのつもりで、標高730付近から東に向かう尾根に入ってしまった。
その結果、ハタチガ沢では三つ目? 主要滝のラストである8m滝の少し下に降りてしまったのだった。
ここらの地形を掴んでいるような振りしているくせに実際は分かってないってことがよ~く自覚できたから、それはそれでよしとするが
降ったところがどこかは分かっても、そこから出会いまでの距離が計れない。
それと足元が滑らないかと下をずっと見て歩いていたので全然楽しくなかった。
そして崩落がありで路面には流木転石転がる荒れた感じの漂うハタチガ林道を下り&15号橋三叉路経由で帰った。
それでも歩いたから、年内はハタチガ沢トレース済みとしてもよいではないか。
たしかに
だが、あそこ、間違って降ったのであって、「あ~ぁぁぁ 俺ってダメだな」との思いが消えずに残る。
その気分を一掃するには
歩き直すのが一番だろう。
それに、たしか いまごろだったような………
そう考えて、ここにした。
そんなだから滝を辿るなんてのはどうでも良い。
ともかくも歩ければ良い。
出入り禁止のガード堅い15号橋を越えること無しにアプローチしようとすると宮ヶ瀬尾根をどこかで越えて入ることになる。
土山峠でバスを降り、座禅石の前を通過して直ぐに湖岸道路から分岐する村道境川林道に入る。
一面に敷き詰められた枯葉を踏みつぶし、日の当たり出した道を進む。
左下の川からもやもや立ち上がるのは川霧か。
秋が深まった証拠だ。
途中に一個所土砂崩れの流砂が道路一杯に埋もれているところもあって、数ヶ月以上は車が走っていないらしい。
路面には小さな穴ぼこ、ひび割れが多数ある。
枯葉のつぶれ具合から歩いてる人も少ないらしい。
枯れ葉の中には同じ色をした小石・石がたくさん混じっていて、自転車でならそんな隠れ石にハンドル取られたり、あるいは踏んでパンクする可能性が高い。
今日はバスだったが、自転車で来たとしても林道入り口に置いて歩いた方が良いだろう。
そんな事を考えてるともう林道終点だ。
ハタチガ沢に入るにはまずは右手の宮ヶ瀬尾根に乗ることになる。
乗って向こう斜面を降ればハタチガ沢、もしくはその支流であるオオユラノ沢だ。
その宮ヶ瀬尾根に乗るには
知っているのは林道終点から先の小瘤を越えて向こう側に降り、直進方向の境川ではなく、右手方向に分かれる小沢に沿って進み、その小沢が左右のどちらにも直ぐ奥に見える砂防堤を見つつ、中央を尾根に乗り、宮ヶ瀬尾根の最低鞍部に出るルートだ。
林道終点から小尾根の経路入口までの距離は二百mくらいだな。
乗り始めだけはザレ地なので道が崩れてしまっているが、見上げれば10m上に丸太の階段が見えてる。
そこに乗りさえすれば道は明瞭だ。
下部は疎林帯中に小豆状の砂の広がる急斜面中にあり、そんな場所だから下部の急傾斜中を降るのは経路の枠組みが土に戻りつつあることもあって気を配る必要があり、雪が積もったならスパイクがあった方が良い。
半分から上部はとても歩きやすくて尾根の最低鞍部に出る。
しかし、いつもいつも、この道というのはどうだろう。
たしかに最低鞍部に直に出るとの特徴はあるが、これが境川林道からの続きとしてのメーンコースとしては踏跡が少ないし、ちょっと険しくて、車道に接続する主要経路としては似合ってない。
 境川林道を行く。車の走った感じが全然無し
境川林道を行く。車の走った感じが全然無し実際にも二カ所くらい崩落があり、車では終点までは入れない
別の経路があるに違いない。
それで林道終点から沢に降りることなく、右手の小尾根を登りだした。
しばらくは踏み跡道だったが、高登差百mほどのところでフイッと手入れのされた作業経路に出た。
地面は適度に固く足に易しくて歩きやすい。
しかし、ずっとコースは植林帯中にあって見通しは利かない。
それに水平なまま湖側に回り込むように悠長な個所もあって、せっかちな俺の波長に合わないかもと、下草がない植林帯中は何処だって道だとして途中で抜け出して最大傾斜を登った。
程なく、黒い角柱にテープが巻かれたのが立っている所で尾根(P597mに続くなだらかな南端)に出た。
角柱は先ほどの経路の出入りの目印らしい。
直登りの距離は長くなかった。
記憶によると、そこらから直に西に降りる経路が踏んであるはずである。
だけど、ここだとハタチガ沢の沢床まで百m程は下降しなくてはならない。
これよりも、南に三百mほど行った宮ヶ瀬尾根の最低鞍部(最初に書いた経路の乗越でもある)からなら50mの下降で沢に降りられるはずだ。
そっちにだって沢に降りる道があると覚えている。
どちらであっても、ここらは足元は岩から砂に変わったザラザラして砂の滑りやすい斜面だから、下りは短ければ短いほど良い。
朽ちかけているとはいえ、経路があるから傾斜とかは気にすることもないが、下りの傾斜もあっちの方が少しだけ緩いような気がした。
色々と考えてそっちにした。
下手な考え、休むに及ばず。
最低鞍部近くで入口を捜す。
そして
経路のようであって、そうでも無いような下りだしだったが、少し行くと経路ははっきりした。
丸太階段用に斜面に打ち込んだ杭木が残っていた。
折り返しにも覚えがあり、丸太階段がまともだったときの下り方を思い出しもできたが、階段部の木は腐ってしまって形無く、斜面中に頭だけがのぞく杭木以外の心細い道だった。
オオユラノ沢に降りて対岸に渡るための丸太橋も無くなっていたし、対岸尾根に登るための経路も形があるようには見えなかった。
でもまあ、オオユラノ沢には降りた。
下流方向に少し行けばハタチガ沢F1出会いに着く。
 宮ヶ瀬尾根から50m下るとオオユラノ沢だ。
ここから三百mほど下流がハタチガ沢への合流点となる。
沢床に降りて、そこを下れば良かったのに
古い経路跡に惑わされて沢床からやや上の右岸斜面を下っていったが良くなかった
宮ヶ瀬尾根から50m下るとオオユラノ沢だ。
ここから三百mほど下流がハタチガ沢への合流点となる。
沢床に降りて、そこを下れば良かったのに
古い経路跡に惑わされて沢床からやや上の右岸斜面を下っていったが良くなかった
オオユラノ沢には大滝はない。
水はあるかないかのレベルに少ない。
沢はフリクションの利くセラドン石を主にして難しいところとかは無い。
だから登っていくのなら駆けてもokとかと言っても大げさでないよう気がする。
しかし下りとなると、二本足で歩いて行けるの良いな。
クライムダウンみたいな格好は取りたくない。
右岸に沢床と平行するように降って行ってハタチガ沢林道に出るための経路があるはず。
そう思いこんでいるからか、斜面中のちょっと段が経路に見える。
岩床を丁寧に歩いても行けるが、少しでも楽をしようとそこに入る。
実際にも経路だったはずで、歩いたことがある。
しかしそれは記憶の道であり、枯葉のつながりが道に似せて見せてはいても、実際には踏幅も無ければ路肩も無し。
踏み込めばザラッと崩れて落ちる小石と砂に靴が一緒になって流れて、「おっと」、両足歩行では足りずに両手を足して斜面をまさぐりる。
気がつけば先ほどまで直ぐ下だった沢床がぐんと下がっていて「ここで滑ったらヤバイゾ」と言う高さになっている。
生きた木の根っ子とかがあれば「やれやれ」と一呼吸入れられるが、ザレ斜面に根っ子は少なく、あっても腐っているのが混じっていて、あんまり頼りにならない。
沢床までの間に段差は無いからすべったら全身擦り傷だろうな。
そうなってから「こんな面倒な思いをするくらいなら、沢床を丁寧に降ったほうがよほど楽だったのに」とごまかしの線のような道跡に入ったのを反省する。
その先をどう進むか、
どうしたら沢床に降りるのが一番安全だろうか、本日一番やばい思いをしたのはここだった。
ようやくほんのちょっとだけ膨らんだ尾根(P597m南端から降ってくる小尾根)に着いたが、そこに上から続いていたはずの道跡も見あたらない。
沢に降りる直前のつぶれてしまった炭焼き窯の中でようやく息をついた。
ここらの木の粘りが元々少ないのか、あるいは湿り気が強い地形なのか丸太製の桟などすぐに腐ってしまうらしい。
一息ついたら沢に降りて対岸に渡り、10mほど露岩の間を行き、降りたら (道路肩用の丸太は形が残っていたが木そのものは腐ってしまっている)
二俣だ。
ハタチガ沢出会い3mcs滝の直登りは怖くて出来ない。
そこで左岸の尾根を15m程登り、そこから尾根を外して10mほど沢に沿って進み、木の根っこを頼りにして5m降ると3mcs滝の上流側10mで沢に戻る。
ハタギガ沢で緊張するのはこのF1の巻きくらいである。
 ハタチガ沢の小滝(緩い)
ハタチガ沢の小滝(緩い)
 ハタチガ沢の小滝
ハタチガ沢の小滝
 ハタチガ沢の滝(8m)
右側から巻くと落口に最短で出られる
ハタチガ沢の滝(8m)
右側から巻くと落口に最短で出られる
 水に濡れないうちに登ってしまえって感じです。(緩い)
水に濡れないうちに登ってしまえって感じです。(緩い)
 二つめの8m滝 遠景
平坦な黒い岩床瀬の向こう側に滝がある
7月に滝の沢を登った後に下ったのがここだった
(写真右手の尾根を下った事になる)
二つめの8m滝 遠景
平坦な黒い岩床瀬の向こう側に滝がある
7月に滝の沢を登った後に下ったのがここだった
(写真右手の尾根を下った事になる)
 8m滝
左側に巻き道あり
8m滝
左側に巻き道あり
枯葉がたくさん散っている。
岩の上も水の流れの中にもたくさんの枯葉が乗って流れている。
黒い岩の上に乗った色味のある葉は漆塗りに乗せた蒔絵のようでもあり、赤黄黒のそういった色使いはかなり好きだ。
セラドン石の岩床と緩いナメ状がハタチガ沢の特徴。
滝らしいのは8m程のが二つある。
一つめの8mはちょっと急なスラブで本体を登るのは難しいが左岸右岸どちらも巻ける。
俺的には巻きの高さが落ち口で済む右の方が好きだ。
滝下からはかなり上まで行かないと沢に戻れないように見えてるが、落口に直に出られる容易な幅広バンド(若干砂地)がある。
二つめの8m滝は左の砂地から巻く。
これも木の根っこが頼りになって余計に登ることなく沢に戻れるて。
どちらも巻き道は易しいとしておこう。
それ以外には、滝には傾斜も高さもそうとう足りない小滝と岩ナメの間に幾つかあるくらい。
入り口は狭いが稜線までの流程も短い。
でも地形図で鍋嵐を中心として眺め、外枠を宮ヶ瀬湖にすると817mの山頂を頂点として第一象限全域のハタチガ沢が占めるように流域が広がっている。
そこではいくつかの小沢(どこも通常ほとんど水は流れていない涸沢だが)が分かれていて、標高817m直下近くまでは全流程が平坦に感じられる沢である。
そんなだからか、稜線に出る間際までには多くの炭焼き窯の跡が残っている。
そこに通うための経路が過去には数え切れないほど沢山あったと思う。
 岩床の中を上流に
岩床の中を上流に
 二俣
左はつぶれた窯です
二俣
左はつぶれた窯です
 沢をふさぐようにピナクル(10m)が立つ
なかなか鋭いが裏からなら(上流側)先端に立てる
左から回り込む(右側からも行ける)
沢をふさぐようにピナクル(10m)が立つ
なかなか鋭いが裏からなら(上流側)先端に立てる
左から回り込む(右側からも行ける)
 沢の詰め
沢は砂の斜面にかわり三方に分かれて、それぞれ稜線に続く
沢の詰め
沢は砂の斜面にかわり三方に分かれて、それぞれ稜線に続く
そんなだからここでは滝よりも岩床を流れる水を楽しむことになる。
つぶれ炭焼き窯の二俣から、
左は稜線(能の爪~鍋嵐のP719m近くへ)までの距離が短い。
詰めがちょっときつかったぞと思い出して右にした。
そこから少しだけ傾斜が増す。
涸棚とは書くが滝には足りない岩床を登る。
もう少しで上の稜線にでるところで沢は三方に分かれて稜線下に食い込んでいく。
中央が鍋嵐に直結する窪地だが、一番顕著な窪地は左であり、そこはいくらか物見峠側によったところで稜線に出るはずだ。
今日は右端の砂地にした。頂上(817m)と北峰(810m)の鞍部に出ることになるはずだ。
岩床の上に崩れ砂が乗っていて、滑りやすいラストとなるだろう。
砂の厚い安定したところを選びたいが、そうもいかない場合もある。
でもまあ、足元が崩れても周囲に及ぶことはないし、多くても二歩分程度で止まるのだから、ものすごくというほどには急ではない。
その程度なのに俺はきつく感じ我慢できなくて砂地が一段落したところで左手の小尾根に移った。
そこも素の岩面が出ているが、登るのを阻むようなのは無い。
岩尾根の表層には木の根っこあり、それも手助けになる。
すぐに鞍部と頂上の間くらいに稜線に出て、山頂がすぐだった。
地面に転がるように置かれている山頂標識を立木にくくりつけられないかとやってみたがうまくいかない。
少しの風なら避けられるかと木の根元に置きなおして頂上を後にした。
物見峠方向へのいつもの道だ。
そしていくつものコースの中から能の爪から宮ヶ瀬尾根を選んで下る。
紫スズランテープ、少し前にも撤去したつもりだったが、最近にも付け直したらしいのが沢山ある。
木の枝にバカ結びに括ったテープを外すには木の間に細枝を差し込みテープがはじけ散るまでグルッと捻って千切れたらポケットに入れる。
全部は取らないよ。
間違い防止になるかと考えらるたのは何カ所かは残した。
でも連続するような無節操なのは基本全部むしった。
結ぶのに手間が掛かったはずだが、外すのにだってそれなりに手間が掛かる。
こんなのがこんなにたくさんあると分かっていれば、外し用のナイフか鉄の細線を持ってきたのに、あり合わせの枝だとサイズをあわせるのにだって一手間かかり、歩いているよりも外している時間の方が長かったかと。
そんなことしてたらP597mに着く頃にはポケットからあふれ落ちて、そこまでの分はバックに納め直した。
これらのテープは新しかった。
もしかして早足したらテープ作業の人に追いつくかも。
まさか、そんなタイミングに人声が届いたりしてさ、ほんとひょっとして、……P597mから降りてきたのは団体(9名)さんだった。
もちろんテープとは関係なし。
彼女らが言うには高い声でおしゃべりして追っ払ってきたので二時間くらいこの付近に熊は無しと、ありがたいことを言ってくれる。
 屋根部分だけが出ている石祠
本来台座のついたそれなりにちゃんとした祠である
掻き出すには用具がないと無理
屋根部分だけが出ている石祠
本来台座のついたそれなりにちゃんとした祠である
掻き出すには用具がないと無理
尾根は北西に向きを変える。(直進すると鹿柵と藪がきつく歩きにくい尾根になる→しばらく下ると左鞍部からの経路に出る)
尾根上に張られた古い鉄線柵を踏みつけつつ、そして降りきった鞍部の樅の木の下にあるのが石祠だ。
ここは十字路、
尾根に沿って前後に進めるし、宮ヶ瀬湖方向に入る道は右下がりに斜面を緩く横断して先ほどの直進尾根に乗って48瀬川の中流に降る。
反対に降ればハタチガ林道に降りていく。
石祠はそんな場所にあって、台座を備えたしっかりした石祠であって、百円玉・五百円のお賽銭が供物台に乗っていたのを見たことがある。
しかし、今は台座どころか胴部もほとんどが砂に埋まってしまい、石屋根が砂の上に出ているだけだ。
山の祠は山の手入れをする人がいなくなると廃れてしまう。
それでもいいのかも。
祭る人があってこその八百万の神様、祠は過去のためにあるのではなく、いまを生きている心の安静のためにあるから、
あがめる人がいなくなったら砂に埋もれお隠れになって過ごすもよしとしましょうよ。
砂を止めている木の根が朽ちて再びの台座が出てくる時までが長いか短いか俺には分からない。
この鞍部からも続く紫のスズランテープ、もしもそれがP617.2mへ続く尾根上ではなく、宮ヶ瀬湖48瀬川方向に下がっていたなら俺はセットした人を 「趣味深い人」 と尊称するだろう。
しかしそんな気配はなく、ノーマルな方向に続いている。
俺がそこを歩いたのだから確かである。
セットの間が遠くなったのは、手持ちのテープが少なくなったか、あるいは既にむしり取った人が通った後だったのか、
それは分からない。
P617.2mからは土山峠方向に降る。
宮ヶ瀬湖が見えているが、木の枝が邪魔になってすっきり見通せないのが気になるが、登りは一切なくて、ずっと降りが続く歩きやすい道である。
標高480mのピーク (標高点ではない) からは土山峠最短となる東方向の尾根を降った。
踏み跡が細くなり、マークも少なかったが、道は(道界杭はある)悪くなく、湖岸直前から作業経路に乗って四十八瀬川左岸に降りた。
 宮ヶ瀬尾根を下りきって湖畔に出た
宮ヶ瀬尾根を下りきって湖畔に出た
 旧道を坂尻(煤ヶ谷)に向かって
歌でもつぶやきながら行くか
旧道を坂尻(煤ヶ谷)に向かって
歌でもつぶやきながら行くか
もしも土山峠から帰る計画だったら自転車でここまで来ていただろう。
そうしなかったのは仏果山を越え、半原に降る予定でいたからだ。
しかし、いざ土山峠につくと仏果山は先日登って、お昼のお茶したばっかりだったし、経ヶ岳も四日くらい前だった
そこをわざわざ登りに行くなんて、
そういう気分になったのは疲れていたからだろう。
それに行ってしまったばかりのバス。
次までの五十分をここで待つのも何だしな、それで時間つぶしに旧土山峠経由で煤ヶ谷まで歩くことにした。
杉林を行く道は枯葉に埋まっている。
その上に照らす日が柔らかく暖かい。
そこを緩く歩いて下る。
法論堂と柿の木平の眺め、辺室山の丸みが何かとっても良くて、いい気分だった気がした。
自宅6:45~千頭橋7:07バス~土山峠~堤川林道~終点からP597m方向に登っていく作業経路へ~稜線(Pm付近)~能の爪方向へ;標高530m付近から~オオユラノ沢に下降着~二俣着~ハタチガ沢~鍋嵐(P817m)着~能の爪~P597m(9人パーティに会う)~P717.2m着~(土山峠方向)~土山峠12:15~旧土山峠~坂尻~役場前(バス乗る)13:05~千頭橋~自宅13:45 20161210 晴れ
トップへ マシラのhp