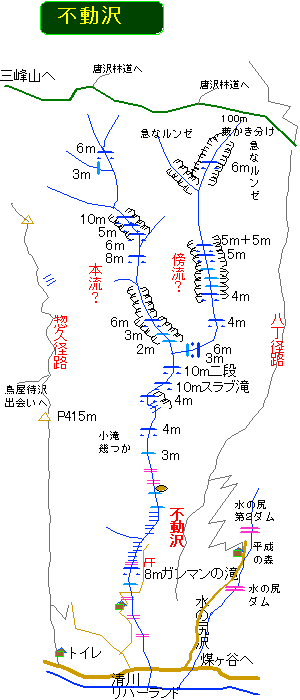丹沢三峰山 不動沢 Ⅴ 左俣
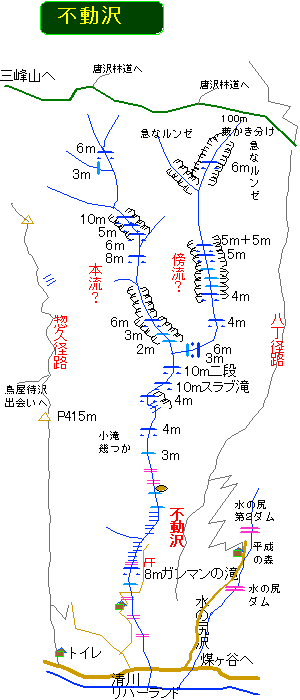
予報では晴れだったように覚えているが、冷たい風が吹きつける大山の方向には何やら寒っぽい雲が漂い、上から射す光が当たってチラチラとひかる。
あれは間違いなく雪雲だ。
桜祭りが始まったというのに風が寒い。
片手を交互に首にあてないと指先が悴んでハンドルがしっかり握れないような感じで自転車のペダルを踏む。
ゆっくり目に走って役場の駐輪場に止める。
不動沢の出会いである「リバーランド」までを少し歩く。
右岸の砂防堤構築道路から入り、堤防下で対岸に渡り、左岸を少し歩いたら再び右岸に移る。
煩雑に方向を探して歩いてるようにも見えるが、実際は明瞭な道(少し前までは車が走れる道だった?)に従って歩くだけだ。
出会いから3百m程の奥に立つ山荘には本日も人影はない。
だけど、まるっきりの無人が長く続いているようなでは無く、時々は人が手入れをしているらしく、小屋の周りは整然といつも整っている。
いったい、どんな人がどんな目的のために、
小屋と言うにはあまりに立派すぎる建物を建てたのだろう。
今度、誰かいるらしい時期に来て聞いてみようかな。
道は再び左岸に移動して、砂の傾斜地に付けられた道を案内標識などを見ながら歩けば自然に「不動の滝」に着く。
不動の滝は6~7mのスラブの滝である。
それほど大きな滝ではない。
下から見上げると滝の右に伸びる岩の上に大きな立ち生一本と祠
があるのが目に付くだろう。
この祠が高々数mの滝を清川村地名抄によれば「ガンマンの滝」と修験の場と称さずには済まさないような雰囲気をあたりにもたらせているようだ。
実際にこの祠の前に立つと滝の高度感がかなりのものに感じられる。
さて、祠内には不動様の石像が立っている。
古来のものは別所に保管されていて、ここは最近に作られたものらしいが、目と口がカッと開き、なかなか愛嬌のある石像だと思う。
祠前に供えられたビール缶とコップ酒を整理し、空いた空間に尾崎のコンビニで買ってきたワンカップの焼酎を追加して供える。
予め供えられていたビールは二本あった。
別種だが缶の裏に印字された製造日は2008年と2009年と一年違いだが、製造日は11月で同じだったから、おそらく同一人物が定期的にここに参って念仏を唱えているんだろうと想像した。
その人が、どんな念仏を唱えたか知らないが、俺もと念仏しようかとしたら、小さいお賽銭箱も付いているのに気がついた。
蓋が開くタイプの箱なので開けてみてみたら小銭が何枚か入っている。
当地では使えない外国の白硬貨も入っている。
それを確かめ、小銭を追加してから春が来たことと山遊びをに来れたことを感謝しつつお念仏を三度唱える。
ここから道は右岸の杉の林の中に移る。
今までよりは幾らか細くはなるが、歩くには全く支障の無い状態が暫く続く。
そのまま歩いても良いが、そうすると滝の数が知れている不動の沢の中では貴重な中流域の小滝を見ないで済ましてしまうことになる。
小滝が見えたところで沢に入り、小滝を越え、岩畳の上を右に左に歩くと流れは左にグッと曲がって50m先で右にもう一度曲がり直す。
この間がゴルジュ状になっていて出口に5m程の滝が一つかかる。
この小滝は水流の少ないときには、多少水量があっても、手がかりは豊富でフリクションは利くのでシャワーを厭わなければ、どうって事無い滝なのだ。
写真削除
 大山には雪雲が舞う
大山には雪雲が舞う だけど、今日は寒い。
山の上から吹き下ろす風は弱いが、寒さは飛びっきり強い。
チラチラと雪が舞っているようにも見える。
こんな日にシャワーを楽しめるのは別人種である。
間違っても仙人もどきにも達しない若輩者だから当然のように、この滝は巻いて登る。
そのまま、ナメも巻いて、左手上方から降りてくる踏み跡道に合流すると、木立の向こうに白く水を落とす滝が見えてくる。
この滝、水量が少ない時期なら、そばまで行かないと気がつかないのだから、今日はやはり水量が相当に多目なのだろう。
その滝は十数mあってトップロープなら登れる可能性があると思う。
だけども、この滝を登った人はいないと思う。
大きなホールドはないが、指先くらいの細かいのはかなりある。
フリクションは砂礫質で問題ない。
層も順だ。
だが、こんなロケーションな所でわざわざ登る必要性を感じる人はまずいないだろう。
修験でも登らないだろう。
知っている限りでは行場としての岩場は世間一般相手の肝試しの域をでていない。
そんな横道は元に戻して先に
滝は右側の礫斜面を登り、小尾根に出たら直ぐに滝方向にトラバースを開始して終始滝を足下に眺めながら落ち口の横にでる。
この巻き道はは薄いながらも踏み跡が付いている。
直ぐに二段の滝下に着く。
段と段の間には小さな釜があり、二段合わせて十mほどの高度差があり、一段目は易しいが、二段目となると直登は難しい。
一段目を登ったら二段目はパスして滝横の立木登りをするか、一番下から滝の右の岩場を登る。
この岩場は純層で岩もしっかりしているので易しく登ることが出来る。
今日は後者だ。
二段の滝を過ぎて50m程奥まった地点で沢は右俣左俣に二分する。
さあ、これからが不動沢の楽しみである。
いままでは疎らにしか滝が無く、それもまともには登れない滝ばっかりなのでつまらないが、三峯界隈の沢は何処も詰めがおもしろいのである。
その分、危険でもあるのだが、その流域にようやく到着だ。
 不動様(ここまではちゃんとした道がある)
不動様(ここまではちゃんとした道がある) 二俣では、左が本流に当たると思うが、右も出会いに滝を架けていてなかなか魅力的である。
その右は前回入った。
左も入ったことはあるが、数年前のことであり、記憶が定かでないので本日は左(本流)とする。
分岐から50m程は狭い沢の中を倒木をくぐり抜けるように歩く。
そして小滝に小ナメ、難しくはないが岩に触るとゾッとするくらいに手が寒い。
幸いに先週の雪の残りは極々小だった。
昨日の雪は、標高900m近辺までは降りはしたが、積もりはしなかったらしく、雪の欠片も感じない。
それよりは今舞っている雪が岩を染めて白くなり始めた。
予報では晴れる事になっているはずだが、現に雪が舞っているとすると、ゆっくりと山の風景を愛でているというようには思わず、さっさと済ましてしまおうという方に気持ちが行ってしまう。
狭い沢は右に曲がる。
 小滝は避ける(登らない)
小滝は避ける(登らない) 右に曲がらず進む直進方向は急な乾いたルンゼ状で、一度入ったことがあるが、三箇所目か四箇所目のCSで追い返されてしまった。
その下降も「落ちる・落ちる」と泣き言を言いながら下ったような手間のかかるもので、本当にあの時はクライミングロープが欲しかった。
そのルンゼを目の前にしたところで右に曲がってスラブ状の滝を登る。
倒木が倒れかかっていたので、それを手がかりにしたので割合と楽に登ることが出来た。
そして奥の分岐だ。
左は右側から覆いかぶさって左側を潰してしまいそうな狭いV字状の急傾斜ルンゼが奥に伸びている。
ここは一度登ったことがある。
出だしは前記のように難しく感じられるが、実際に取り付いてみると岩は割合に硬く、傾斜はソコソコであり、分岐での印象ほどには悪くはない。
右は本来の本流である。
最初左に行こうとしたが、入った記憶が戻ってきて、今日はまだ歩いたことのない右に入ることにする。
さあ、これからだ。
気合いを入れていこう。
 奥の分岐の左側のルンゼ(快適な登りです)本日は見るだけ
奥の分岐の左側のルンゼ(快適な登りです)本日は見るだけ 小滝が一個二個三個四個。小滝だが実際に登ってみると、ホールドは乏しく急なのでかなり手強い。
ただフリクションは飛びっきり良く、ちょっとだけ靴が引っかかればまずは滑らないのと、岩がどうしてもダメな場合は小滝に倒木を立てさえすれば梯子登りが可能ということで岩の冷たさはいかんともしがたいが、岩の感触が楽しめるので悪くはなかった。
でも、このまま終わるならヤッパリさっきのV字ルンゼにしとけば、もう少し岩の感触が楽しめたかなあと反省しかかったころに前方が急傾斜になって上方に三段の滝が見えてくる。
急だ。
山の詰めで急な涸棚なんて、危険だと思ったらさっさと巻いてしまえば良い。
だけど、そばまで行って、近くで見てみたいんだよなあ、マシラって。
それに今日は、もうほとんど沢の詰めの稜線下というのに先日の降雪の名残なのか、岩の上を水がしたたり落ちて滝のようになっているんだ。
そいつが「オイデおいで見においで」と手招きするのだから、巻こうかなと考えていても、もう少し「ちょっとだけ」と沢からなかなか離れられなく、ついつい滝のそばに寄って行ってしまうのだ。
 奥の分岐では右へ 見た目よりは難しい小滝 樋状にCSは避けられない
奥の分岐では右へ 見た目よりは難しい小滝 樋状にCSは避けられない そうやって近づいてみた三段の滝は、三段とも水は空中を落下していて急だった。
見たならさっさと巻いて と
だけど良く見たら登れそうな気もする。
滝をダイレクトに登るのは無理だが、一段目は左から取り付いて右にトラバースすれば上にでる事ができて、そこから二段目下を右に移って三段目下にトラバース仕直すことで左の立木帯にでる。
そこからは立木(根っ子)登りが可能じゃないかってルート設定できてしまった。
行こうか止めようか。
登りの途中で止めておけばと後悔したことが今までに何回もある。
ザレ場登りは無事に登れればよいが、退却となった場合に確保用ロープなど持ってないから本当にしんどいのだ。
 三段滝 とても高く急に見える。どうやって越えるんだろうか
三段滝 とても高く急に見える。どうやって越えるんだろうか だけど、こういう状況の時に最初から止めたと決め、行動に移せたことはほとんど無い。
山歩き愛好者の常として、イヤダイヤダと言いつつヤッパリ登ってしまうのである。
やめよう止めよと頭の中では思っていても、いざその場に来れば行ってしまいたい本能が勝ってしまって、今日もその轍を外しはしないだ。
あ~ぁダメ
三段の滝はそう思いながら、想定したとおりに登った。
想定と違った点は、三段目から上の斜面が思った以上に急傾斜で長かったことで、何カ所か、どう回避したらよいのか考えながら登ったのだった。
三段滝を半分は巻き気味に登って小尾根に着く。
そこか見渡せる沢には緩い滝に小ナメがあるだけで、そのまま稜線に詰めて行きそうな感じだったので、一旦は沢を終え、このまま小尾根を登って行こうかとも思ったが、沢にはなんがあるか分からないのである。
行けるのであれば、ともかくも行こう。
そんな気持ちで崩れかかっている露岩が剥き出しのトラバース道を横行して沢に戻る。
その甲斐あって小ナメの岩の上を歩くことが出来たし、その先には6m程の滝をも見る事が出来た。
その6m滝は傾斜がきつく登れない。
左から素礫の斜面を登り、小尾根に出る。
右下にその沢を眺めながら100m程瘤尾根を詰める。
左手に尾根が近づいてきたところについている薄い踏み跡をたどってそちらに横行する。
そして大きな黒樅の木が立つ地点で尾根(惣久径路を上に直進する尾根)にでた。
上の登山道(物見峠~三峰山)までは三~四分の距離である。
上の登山道から、この尾根に入るポイントは煤竹の中であり、知っていれば分かるが、知らないと目印はないので分かりにくい。
登山道を三峰山から物見峠に向かう場合、左手方向が崩落地となって丸太で補強された部分の中央付近の竹藪の中とでも言っておこう。
 これが沢の最後の涸棚 7mくらいかな 左から巻く
これが沢の最後の涸棚 7mくらいかな 左から巻く 本日は晴れると言っていた。
だから、狙いでは桶嵐沢に下る尾根に入って、その先は……と予定していたが、尾根には雪が舞っていた。足元が不安定にならないうちにというのを理由に、先ほど登ってきた尾根を元に戻り、そのまま下って惣久径路に入り、P415m手前の鞍部から小山の坂と称す径路を200m程辿って鳥屋待沢沿いの仕事道を歩いて谷太郎川林道に出て役場に戻る。
日が時々は射すが、自転車で受ける風は冷たく、飯山界隈には桜祭りの交通整理の人も出ているが、肝心の桜は開きかかったところで成長を止めているようで蕾の大きさはほとんどそのままに、今年は桜を長く見ることが出来そうな感じがした。
 尾根(惣久尾根の上方)に出て木の下で一休み
尾根(惣久尾根の上方)に出て木の下で一休み
 木の葉の芽吹き(ヤッパリ春がきた)
木の葉の芽吹き(ヤッパリ春がきた)前回
不動沢(三峰 寺家) 080921
不動沢(三峰 寺家) 2007/03/31
不動沢(三峰)2004/07/18
不動沢(三峰) 1999/11/13
自宅5:50~清川村役場に自転車デポ)6:30~リバーランド(不動沢出会)6:45~不動の滝(ガンマンの滝)7:00_15~幅広の滝7:50_55~二俣(左本流へ)8:05~分岐(左を探索8:20_30後に右へ)~三段滝の上8:50~最後の6m滝9:10~尾根に出る9:25(惣久径路上部)~登山道に合流9:30~折り返し~惣久径路~P415m手前鞍部9:50~鳥屋待沢9:55~出会10:05~谷太郎川林道~役場10:20~自宅10:45 20100327
春 桜咲く だけど吹く風も沢の岩もとても冷たく、沢の詰めには雪も舞っていて本当に春なんだろうかと感じる日でした。
頁トップへ マシラのHP