丹沢大山小唐沢橋から北尾根のピーク周回 (佐久間送電鉄塔沿いにミズヒの頭経由)
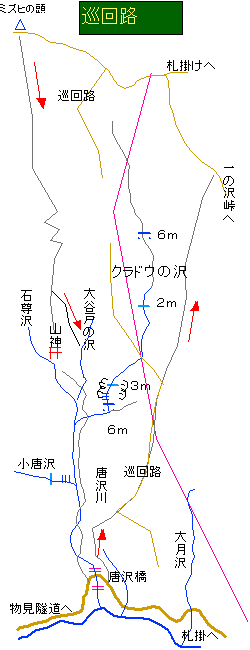
薄く土色に塗られている鉄塔でさえ、その気になって確認しなければモノトーンの中にじっと自然の造形物のように収まり、上空の雲からは湧いて出るように雪が降ってくる。見渡せば雲の間から普段見ているのとは違う水墨画のような山々が見える。風はない。とても静かだ。その静寂を破って谷間に響く音は氷の重さに絶えかねて折れて落ちる大木の枝の悲鳴か。<18号鉄塔>
子どもの頃、家から少し離れた畑の中に高さ7mほどの送電鉄塔が直線上に並んで建っていた。見えないほど遠くの知らない発電所からの電気が山を越えて隣の町まで送られているとは聞いたが、始点も終点もどこにあるのかは知らない。危ないから決して登らないようにとは注意を受けていた。
小学生の高学年の頃に山の上に大きな鉄塔が立ち、そこに送電線が張られると、畑の中の送電線は外された。鉄塔は払い下げられ、そのうちの一本を受けた隣の鉄工所のおやじが形を変え、一部は我が家の物干し台になった。以上、私の鉄塔の思い出である。
さあ次に行こうか。巡視路のステップに乗って歩き出す。
雨が降ってくるなら、すぐに帰ると言って玄関を出た瞬間から霧のような雨が降っていた。約束通りなら、この場で帰ることになるのだろうが、ポツポツと雪も交じっているように見えたから、山の上はおそらく雪だろう。そのとおりに山が雪であれば、約束を違えたことにはならないのだから、まずは山まで行くのだ。山が雨なら帰ろう。
煤ヶ谷でバスを降りたときには、細かな雨のような雪のようなみぞれ状態だったが、山の中に入ると、程なく雪に変わった。登るにつれてサラサラの雪に変わり、雨のように濡れる心配はなくなった。
林の中で枯れ葉の上に積もりだし、トラバースが始まる頃には全くの雪の世界になった。積もった厚さは2cm以上5cm以下かな。標高というより、場所によって降雪量は変化して物見峠に近づくに従って雪は少なくなる。ここらあたりだと先週に降った雪はほとんどが解けて無くなり、昨日・一昨日の平地の雨は山でも雨だったように思えた。
物見峠から隧道に下りて唐沢林道を歩く。積雪は少なくとも、蹴散らすようにして最初に踏み跡を付けるのはなんとも気持ちの良いもので、歩幅もついつい伸びる。途中で丸淵を旧の作業道から降りて確認してから、新の作業道で林道に戻る。丸淵に行っている間に車一台が走った跡を着け、札掛け方向からも一台がやってきて小唐沢橋の上で出会った。
<20120701写真削除>
物見峠付近は雪景色
本日のコースは、ここから右手の尾根に上がり、P602mを経由してクラドウの沢(右岸尾根には17号鉄塔がある)の右側に当たる、細く小さな左岸尾根を北尾根に上がることである。そこから北尾根16号鉄塔の一つ大山側のピーク(標高約1040mミズヒの頭)まで行ってから、北北東に伸びる尾根(17号鉄塔の建つ尾根から間に小沢を挟んだ一つ大山側の尾根)を伝って唐沢川の山神様へダイレクトに下降して参ろうというルートである。その先は三峰山経由かな。
 丸淵は少しだけ砂が薄くなっているかな
丸淵は少しだけ砂が薄くなっているかな 橋から、どこか取り付くのに良い場所はと見定めて、橋の袂から10mの位置から斜面に入る。杉の林の中を、雪に覆われてからこそハッキリするような踏跡を登る。斜面は直ぐに小尾根状に変わるが、曲がりくねって這える馬酔木の葉っぱに雪がへばりついていて揺するとバラバラと落ちて来て首筋から入り込むので、それを何とか避けようとすると枝を払うのが煩わしい。それに小尾根は短い距離だが、途中に露岩が乗っかっていて険しく複雑だ。別の場所から登った方がよかったかなあ。程なく右の小沢の斜面を小さくトラバースする。右からはその小窪が、左の唐沢川からも小窪が上がってきて、そこに小尾根が合流している地点で尾根に戻る。こんな場所は普通なら岩道になるはずなのに、これから登る急傾斜の足休めの為にあつらえたような平坦部になっている。
<写真削除しました 20110502>
小唐沢橋の横から登り始める
尾根は直上できず、右の斜面をトラバースして100mも登っていくと右から上がってくる小尾根のテープの目印が木に巻き付けられたところで踏み跡道に合流する。付近の雪量は物見峠あたりの方が多かったかな。602mは目印のテープ以外は何もない小山だった。
傾斜の緩くなった尾根を歩く。木立の中で見通しは利かず、雪を馬酔木の葉っぱが受けて、それが歩くにつれてバラバラと体にかかる。ダラダラと歩き、木々の向こうに突然幕が開いたかのようにして鉄塔に到着する(新多摩線18号鉄塔)送電線は前も後ろも一つ先の鉄塔までは何とか分かるが、その先は空の雪に吸い込まれてしまっているようにして見えない。
<写真削除しました 20110502>
18号鉄塔に付く 完璧にモノトーンの世界だ
さあ方向はどっちだっけ。進むべき方向は17号鉄塔につながる送電線の下に沿って巡視路は伸びるが、そのままに歩くと、今日の目的の方向からは外れてしまう。送電線の下の少し右側に行くのが本来の方向なのだ。巡視路に従って一旦はクラドウの沢に入ってから方向を変えて行くしかないのかな。ステップ付きの巡回道を鞍部まで降ってから、方向に自信が無くなり鉄塔まで戻って進むべき方向を改めて再確認する。送電線の付近というのは鉄塔や送電線を基準にして、現在地を確認できるのが何と言っても強みなのだ。これに地図を持っていれば心強いのだが。そして方向を決める。
<写真削除しました 20110502>
クラドウの沢の巡視路から17号鉄塔を見上げる
巡視路は鞍部から尾根の左斜面を徐々に登るようにして、でも正面の尾根を外してクラドウの沢に入っていく。クラドウの沢は歩いたことがある。そこは上を見れば空を裂くように送電線がうざったく伸びている沢で、難しいところは無く、雪がない時期なら乾いて、がらがらした沢である。
今日は送電路を歩きにきたのではない。クラドウの沢左岸に小さな瘤のような尾根があり、それは距離1km程の先の標高線790m付近で北尾根に合するそれが目的のルートだ。
小唐沢橋から山に入り、602mから歩いてきて、尾根の連なりに従って大山にまで登るとなると、クラドウの沢を横断するのは横道であり、この尾根を登るのが本道だろう。その道に入るのである。
クラドウの沢に入る巡回路を確認してから、50mほど戻って、その尾根に入る。自宅で確認した地図の上では小さな尾根だったが、実際も左がクラドウの沢、右にも小窪(大月橋が唐沢林道にある大月橋から上がってくる火打沢?)が尾根に沿って上がってくる狭くて小さな尾根である。マークの存在には全く気がつかなかったが、周囲は杉・檜・茅などの植林帯であり、人が歩いてつけた踏み跡道があり、藪に煩わしい思いをする事はなかった。小さい尾根の分だけ方向を外すこともなくハッキリとしている。拾った木の枝を1m程の長さに折り、シュリンゲをインクノットで結んで杖紐にして手を通した杖にして、それを頼りにして雪を掴まないようにして登る。
<写真削除しました 20110502>
クラドウの沢左岸尾根を北尾根目指して登る(等高線790m付近で合流するはずだ)
マークテープ類は一切無いが、仕事よう踏み跡はある
北尾根が近づくに従い、下の土が硬くなってくのが分かる。尖った杖を地面に着くとツルッと滑る事が多くなる。北尾根(標高700m以上)付近は今舞っている雪の下に、前に降った雪が解けずに残っているらしく、それが昨日一昨日に降った雨が浸みこんで冷気で凍り付きカチカチの状態だった。実際に地面だけでなく、バランスのために掴もうとする立木もすべてが幹の表面には水氷が一周へばりついていて、その上の谷側だけに雪が付着している。それを掴もうとすれば、親指とその他の指をくるっと幹に回して握力を込めて握らないと、バランスの手助けにならないのだ。
そんなだから、下では軽く触っただけでバラバラと落ちてきていた木に付く樹氷や葉の上の雪も、ここではガチガチに固くこびり付いているようで、軽く揺するくらいでは欠片も落ちてこないのだ。
<20120701写真削除>
北尾根に合流 尾根には残雪があり凍っていて、その上に新雪が乗っている
だからか、北尾根を歩くのはかなり緊張した。北尾根は日のあたりが弱く、歩く人も少ないはずだから、凍り付くような場所はないから楽勝なんて考えてきたけど、実際は雪の残りがカチカチに凍った上に新雪が乗っていて、普通な言い方をすればスリップしやすい極めて危険な状態だった。安全に楽に歩こうというのであれば六本で良いからアイゼンを持ってくるべきである。
マシラ 家にも持ってないけどね。
それに運動靴も問題だ。夏の沢歩き用のママなんだ。ソール厚さが3mmくらいしかない。下が堅い道を歩くと苦痛。それに寒く、先週はかなり寒さに参った。それで今日は対策として靴下を二枚重ねて履いてきた。おかげで足は寒くないけど、浅い溝のソールは凍結した登山道ではスリップの役に立ちそうもなく、その分だけ慎重に歩く事を強いられるのだ。そんな場所が断続的にあって、尾根歩きは気が休まらない。
尾根に乗って間になくP913m(16号鉄塔)に到着する。17号の巡視路入り口を過ぎて20分ほどで、北尾根の次のピーク(1040m?ミズヒの頭)に到着だ。
<20120701写真削除>
16号鉄塔 氷の鎧の中に立つようだ
さあここからが次の目的である山神様への巡礼道である。
それは北北東に延びる尾根を降り、山神様の鎮座まします台地にダイレクトに下降しようというものである。著名な大山北尾根だから、地図上ではささやかなこの小尾根にも名前があるのだろうけど知らない。
<写真削除しました 20110502>
ミズヒの頭(等高線1040mのピーク)バリバリに凍結し、雪は結晶化して細く鋭く伸びている
この尾根の降り出しは色々と頼りなかった。
まず、その一つ目は雪の下の残雪が固く凍っていること。降り初めのうちは特に固く、靴は少しも雪にけり込めず、ツルツルにタジタジした。そんな場合は木の枝が頼りなのだが、寒さで凍っている枝なんて、ちょっとした圧力で裂けてしまうから、太いというだけでは安心できない。滑ったらこの場合には、どこでつまるんだろうかなんて真剣に心配しなければならなかった。もしも、この状態が20mも続いたら、このコースの下降は諦めていたと思う。その場合で一番安全なコースは大山まで行くことかな。凍結した場合には北尾根の下降もけっして安心できるコースではない。
最初の20mが過ぎると、幾らか氷が柔らかくなる。踵を土にけりつけて、靴を雪にめり込ませて下る。蹴りこみが利けばいいけど、まだ固い氷に跳ね返される箇所も混じっていて稜線から200mくらい下までは気を休めることが出来ないのだ。
<写真削除しました 20110502>
ミズヒの頭から唐沢川の山神様に向けて一直線に下降するのだ。雪がなかったら面倒そうだな
二つ目としては、尾根が小さく不鮮明なので、この方向で下っていって間違いないのか心細いことである。降り始めの最初もそうだったが、下に付くまで、尾根が明確な場所なんて、ほとんど無くて、ずっとここで良いんだろうかという降りを続けるのだ。こんな時にこそ頼りになるのは先行者のマークテープで下までの間に二箇所あったが、そこにはマジックで「この先キケン」と書かれていて、どうなるんだろうと気になってしまい、あたりを楽しむ余裕なんてない。 実際、尾根状は保っていても、大岩の乗った危ない状態で下に落ち込んでいる二箇所・三箇所は側面を巻くようにして下る。雪はあっても氷が無くなり、雪の下の砂が踏ん張れるので何とかなるけど、もしも地面が凍っていたら、この降りは難儀しただろう。
下が近くなったころに尾根通しの下降はきつくなり、左手の沢状にトラバースして入る。沢は雪が残っていて腰下までにもなるが100m程で唐沢川の見覚えのある炭焼窯の上に立つ。
その場所から山神様までは30m程の位置だったから、まあまあ予定通りに下降できたことになる。
 山神様の石祠は相も変わらずに鎮座ましています。
山神様の石祠は相も変わらずに鎮座ましています。 周囲の木立は鎮守の森のようだ。川の流れの水音は10mも離れると空間に吸い込まれていき、雪の中の石祠は寂しい。
<写真削除しました 20110502>
牛頭観音様も雪の中に静かにひっそりと(小唐沢橋から五分ほどの位置)
これで予定のコースの半分は終わった。この先は三峰に登って帰る予定だったが、三峰からの降りは一般道でもあっても凍り付いている場所がたくさんあり、そこがかなり危ないのではないだろうか。もっとたくさん雪が降っていれば、それががスリップ止めになるので安全性が増すが、薄雪の下が固く凍っている場所を絶対に大丈夫といって下降する自信なんてのは無い。
以上をまとめて、
ミズヒの頭からの降りくらいで神経がめい一杯になってしまうマシラのキョパシティは今日はもう十分歩いたでしょうと頭の左から右にささやくのだ。そうすると山神様をちょっと違ったコースから巡回する目的も果たしたんだし、山を下ってくると雪が少し雨っぽく感じるようにもなって、今までは全く濡れていないがこの先は雨に変わるかも分からない。さあさ帰ろうよ。と反応するのである。時間的にも良い時間だしな。
<写真削除しました 20110502>
唐沢林道から仕事路(整備中)を下る
唐沢川を降り、小唐沢橋に出て唐沢林道を歩く。物見隧道を通過して、途中で小尾根道に入ったら、工事中の仕事道は予定していた辺室沢沿いに下るのではなく、下に唐沢林道入り口ゲート下の犬舎が建つ家の小川を挟んだ山側に降りていた。犬が吠え出す。このまま、その犬舎に向かったらいっそう吠えるに違いないと車の走れる林道に従って唐沢林道入り口ゲートまで行ったので、これなら、この仕事道に入らずに唐沢林道をそのまま下れば良かった。
大通りに出ても、犬舎の犬の鳴き声がしつこいので、どうしてだろうと覗き込んだら、猿に犬がからかわれているのだった。鎖に繋がれているのを良いことに、鎖の先の3mくらいの位置に立つ柵の柱にボスらしきのが、その周囲に三匹ほども陣取って座り、犬に向かってキバを剥いて挑発しているのだった。鎖に繋がれて飼い主が不在の犬は悲しい。猿は知恵者で底意地が悪い。アッ イヤ マシラも猿だ。近い種ほど些細な違いを拡大していがみあうというから、マシラとて似たような事やって、誰かに底意地が悪いと後ろ指さされているかもしれないな。
赤いのや白い梅の花は咲いているが、なんか寒々として見える坂尻からバスに乗る。
自宅6:40〜上千頭橋7:10バス乗車〜煤ヶ谷7:30〜登山道〜物見峠8:15〜物見隧道8:20〜丸淵見学8:35_45〜小唐沢橋8:55〜尾根に入る〜P602m9:20〜18号鉄塔9:25_30〜クラドウの沢9:45〜戻ってクラドウの沢左岸尾根に9:50〜北尾根に合流(h790m付近)10:00〜16号鉄塔10:15〜北尾根1040mのピーク(ミズヒの頭)10:30_35〜北北東尾根下降〜山神様に到着11:10_15〜千頭観音11:40〜小唐沢橋11:45〜物見隧道12:10〜唐沢林道〜h370m付近から仕事道へ(幅1.5m整備中でとても良い道です)12:30〜犬舎裏へ12:40〜泥道〜唐沢林道入口ゲート12:45〜坂尻BS13:10〜BS下車13:30〜自宅13:50 2010/02/13 下では雨に雪だが、山では雪 今回の降雪量は物見峠3cm 唐沢林道2〜5cm 山神様3cm
頁トップへ マシラのHP
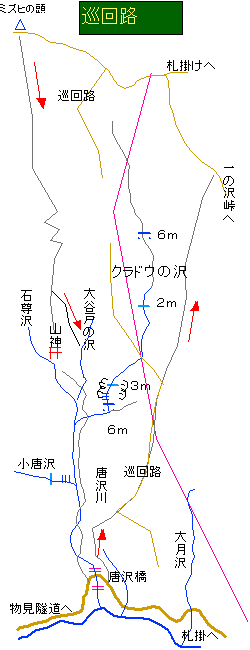 薄く土色に塗られている鉄塔でさえ、その気になって確認しなければモノトーンの中にじっと自然の造形物のように収まり、上空の雲からは湧いて出るように雪が降ってくる。見渡せば雲の間から普段見ているのとは違う水墨画のような山々が見える。風はない。とても静かだ。その静寂を破って谷間に響く音は氷の重さに絶えかねて折れて落ちる大木の枝の悲鳴か。<18号鉄塔>
薄く土色に塗られている鉄塔でさえ、その気になって確認しなければモノトーンの中にじっと自然の造形物のように収まり、上空の雲からは湧いて出るように雪が降ってくる。見渡せば雲の間から普段見ているのとは違う水墨画のような山々が見える。風はない。とても静かだ。その静寂を破って谷間に響く音は氷の重さに絶えかねて折れて落ちる大木の枝の悲鳴か。<18号鉄塔>
