丹沢の里沢歩き 広沢寺 山神沢 に遊ぶ マシラ
正月
一日目 親のところに出かける。
二日目 帰ってきた娘が三日目から仕事だというので駅まで送る。
道すがら、昔、親から言われた言葉を娘に言う自分がいる。
さだまさしの「案山子」の言葉そのままだ。
最後のフレーズは付け加えだが。
娘との別れ際、わが親のこころがようやく分かったような気がする。
昨日、もう少しゆっくりしてくれば良かったなあ。
次はもっと話しをしよう。
改札機の向こうで笑って手を振り、エスカレータで上がって姿が見えなくなるのを見届けてから歩いて自宅に帰る。
心配するなとは言うけど、清貧を絵に描いたよう生活が危なっかしく思えてしょうがない。
自分で決めた好きなことやってるから、あの子はお金無くとも綺麗なおべべ着なくてもぜんぜん大丈夫よと妻はいう。
けれども何かと心配する自分がいる。
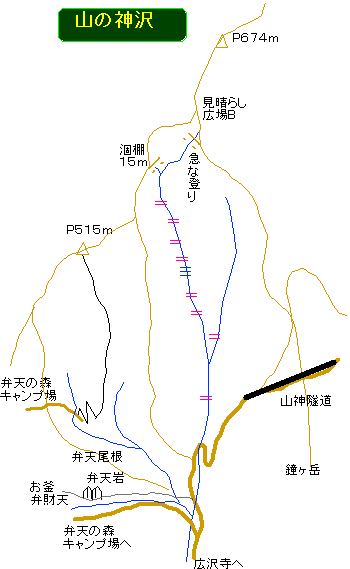
さて、新年の最初の山は初詣だ。
近場で楽にと、場所は鐘ヶ岳浅間神社。
選択理由は田舎のと同じく木花咲耶姫命と大山祇命を祀った神社だから。
鐘ヶ岳は表参道に裏参道、厚木市の教育施設奥の林道から、金翅川の左右、それに北尾根と言うコースも取れる。
そのうちの、とりあえず北尾根と言われる所に行こうと思った。
その場合、尾根の末端は煤ヶ谷付近だが、下部に豚舎とかがあって取り付くのが面倒そうだから、楽に行けるのはということで別所の湯から林道を歩き、林道が尽きたところから適当に山の背に乗って、鐘ヶ岳山頂まで行った。
P420mと、その北300mの小ピーク(P400m)は間違いなく通ったが、それより下の部分は北尾根を登ったのか、違うとこ通ったんだかが実はよく分からない。
分からないけど、神社の鬼門って聞いたこと無いから気にしない。
で歩いたとこって、山の背状態の部分は道はハッキリしていたが、急斜面は踏み跡不明瞭だった。
しかし、昔からたくさんの人が登っているから普通に困るような地形はなく、別所の湯から50分、林道終点から40分ほどで山頂に着いた。
途中、小ピークから下山中の人と遭遇したのがアクセントになった感じだ。
山頂の浅間神社には二礼二拝に加えて、鈴を鳴らし賽銭箱に小銭を投げては神様の耳をこちらに向けさせ、木花咲耶姫命には家内安全と一族郎党の繁栄?を、大山祇命には特に山の厄除けを中心にお願いする。
願い事が終わったら下山である。
ただし、今日の下山路は次のアプローチに当たる。
鐘ヶ岳の参拝者用手水舎の横から大山側の斜面を下る。
下地は砂に小石の混じった礫状の斜面で滑りやすい。
立木は適度にあるが、いちいち手がかりにしていたら時間もかかるし手も疲れるのでバランスを取るためにだけに使う。
人が付けたか獣道なのか、適当に踏み跡らしきものがあれば、その跡に乗っかる。
斜面は急で、どちらかといえば、下流側にトラバース気味に下降していく形になる。
それでも小さな尾根に乗っかると、ようやくちゃんとした道らしくなる。
ただ、直ぐに下に林道が見えてくる。
林道に着く前に壊れかかった仕事小屋を確認する。
降りた地点は大平の石切場の標識の上流側50m、廃屋から50m下流の地点だった。
予想よりも下流だったが、アプローチとしてはまあまあの位置である。
 山神沢はこんな感じだ
山神沢はこんな感じだ さてと、山の神隧道への林道を奥に向かって登る。
車止めゲートの先で車道は右に曲がって行くが、山の神沢は直進する。
今日はこの山の神沢である。
おそらく滝は無い。
でも詰めはヤバイかもしれないから用心が必要だ。
仕事道が右岸の鹿柵沿いにしばらく平行に進む。
その道を無視して沢の石の上を歩く。
割れて角だった石が集積したところを見ると山の地質が脆く急であることと、斜面から落ちてきた石が水流に押し出されて転がって磨かれるなんてことがメッタに起きない流水の少ない場所であることを示している。
だからといって土砂の流下を堰きとめる砂防堤が不要かと言えばちょっと違う。
この沢には砂防堤が見た範囲で8個もあるのだ。
支流の分を入れれば倍になるかも知れない。滝
は全くないが砂防堤は沢山ある沢なのである。
ゲートからしばらく進んだところの砂防堤を越えると、それまで狭かった沢は開けて明るくなる。
その先で仕事道は左の斜面に上がっていき、沢沿いの道はか細いものとなって三俣に達する。
 急な岩溝が山肌を駆け上っていく
急な岩溝が山肌を駆け上っていく 右にはコンクリ製の古い砂防堤が一つ立つ。
昭和40年代のより古い砂防堤の工事銘版を見ることはメッタにない。
この流域の砂防堤もコンクリ製だが銘版が無い。
コンクリのやけ具合からもおそらく昭和30年代の構築物かなと想像する。実際はどうだか分からないけどね。
小さな沢の10m近い高さの砂防堤は守るべきものに対して大げさに見えるが大水が出たときは、これでも貧弱に見えるのかもしれない。
その砂防堤を確認し戻って、三俣の中で一番沢床が低く幅が広そうな中央の窪みに入る。
そこは少しだけれども水も流れている。
さっきのと同じ構造の砂防堤が二個あり、間にナメ状を一つ挟んで、更に砂防堤が等間隔の間をあけて四個続く。
その四個目を登り終えると左に涸棚15mが立つ。
涸棚の上は浅い露岩の凹状になって急傾斜のまま山稜に達している。
本流は幅広い傾斜地の中の露岩を幅2m程の溝に掘ったような感じの登りとなる。
急だが、ゴツゴツした露岩の積み重ねた状態なので登るのは易しい。
もしも溝を外れて登ろうとなると露岩にまぶされて砂の上を歩くことになるので不安定なので溝の中の方がよっぽど歩きやすい。
ただし、200m程この溝を登っていった先は両岸から挟まれた井戸の底から急に立ち上がったような15m程の涸棚状があり、尋常な手段では登れそうもない形で稜線に直結する。
ここは登れない。
 沢のどん詰まり(稜線下)はとても急なのだ
沢のどん詰まり(稜線下)はとても急なのだ 遠くで猟犬の鳴く声が聞こえた。
山の中で迷子になって飼い主を鳴いて呼んでいるのだろうか。
どうもこれから行く方向にいるらしい。
面倒にならなければよいがと思う。
それは詰めのことか、犬のことかときかれれば両方ともと言っておこう。
詰めの最後が、そんな状態だなと見て取れたところで、20m程下がって、左の砂と岩の斜面を登ることにする。
そこは傾斜はきついが木の根っ子も適度にあるので、腐れ木を掴まないことを確認していれば、格段に難しくはない。
ただし、砂礫地を登りきった後に先ほどの最終地の涸棚上を左から右に横断する獣道の通りに歩くのが一番楽に見えるのだが、露岩の上に乗った砂が薄く、砂の上で滑る感じがして靴が定まらない感じがして、下が空中になっていることもあって我ながら気持ちがビビッテしまう怖さがあった。
この5mの横断が一番怖かった。
実際、下に涸棚があると思わなければ、サッササのさと1秒で通過してしまうだろうに。
そして稜線に着く。
高い方に30m程歩くと見晴らし広場B(鐘ヶ岳方面と弁天の森キャンプ場方面の分岐:西端にP674mあり)に出る。
さてと、この先もと考えていたが、この沢が滝はなかったけど、想像していたよりきつかったこともあり、ここまでとする。
弁天の森方向のP515m迄行き、そこでさっき吠えていた犬に遭遇する。
どうってことなかったけどさ。
正月の殺生禁止期間と言うこともあり、飼い主が山の散歩にと繰り出し、首輪を外したら犬が勝手知った我が道ということで、尾根を駆け上り、そこで飼い主が来るのを今か今かと催促して吠えていたのだった。
人の周りをグルグル回り匂いを嗅ぎまくりじゃまくさいので
と杖で方向を示したら、飼い主を呼びに駆けていった。やれやれだ。
 広沢寺から鐘ヶ岳を見る。この後は巡礼峠を通って自宅まで歩く
広沢寺から鐘ヶ岳を見る。この後は巡礼峠を通って自宅まで歩く 更に東進して弁天尾根に入る。
弁天岩に寄ろうと思っていたが、気がつけば下降点を通過してしまっていた。
だが、わざわざ戻ってまでして寄っていく用は無いので直進して大釜弁財天参道(旧道)入り口に出る。
とりあえず山歩きはいったん、ここで終わりだ。
バスに乗って帰っても、巡礼峠から飯山観音を経て帰っても時間的には変わらないではないかと思い直し、それならばと飯山観音への山越え道を選んだ。
そこは厚木の町では超有名なハイキングコースである。
良い道であり、道なんか絶対に間違わないのだ。
と、うぬぼれていたら通りかかった人に七沢からの巡礼道の入り口を尋ねられ、間違えて教えてしまった。
ははは
ハイキングコース侮れず。
訂正のために戻って案内し直しと思わぬ道草をしてしまった。
一人だと道を間違えても、自分に降り懸かるだけだが、子ども連れに間違った道を教えたことには平然としてはいられない。
今年もも、こんなそそっかしい間違いを繰り返しながら山に行くんだろうな。
とほほ
せいぜい 笑っておくんなさい。
年の初めだし、笑う門には福来たるっていうから。
笑うのは悪いことではないよ。
自宅6:40〜千頭橋7:07バス〜別所温泉入り口〜鐘ヶ岳8:15〜神社参拝8:20〜大平8:40〜車止めゲート8:50〜山の神沢〜稜線9:50〜見晴らし広場B9:55〜弁天尾根10:25〜大釜弁財天入口10;40〜広沢寺入り口11:25〜巡礼峠11:25〜飯山神社入口12:10〜自宅まで歩く13:00 20100103 割と暖かい正月かな 晴れ
頁トップへ マシラのHP
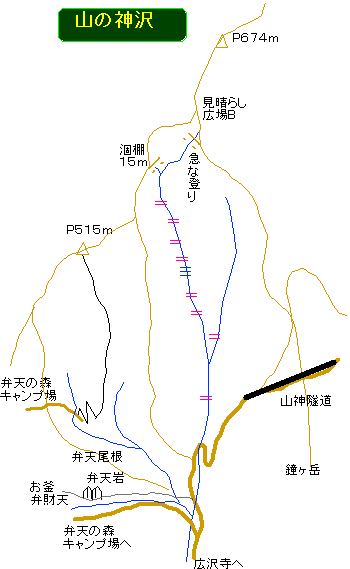 さて、新年の最初の山は初詣だ。
さて、新年の最初の山は初詣だ。


